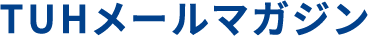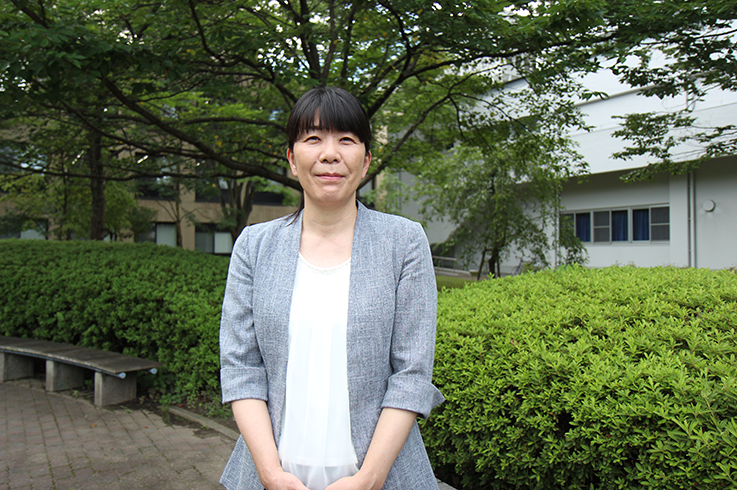言語聴覚士を目指すきっかけは?
学生時代に父が脳梗塞で倒れて閉じ込め症候群(*1)になったのですが、父が食べられるように担当の看護師さんが一生懸命に努力してくださって。ジュースを一口舐めることができただけで喜ぶ父の姿を見て、自分も専門知識を身に付けて少しでも嚥下について理解できるようになりたいと思いました。その頃、大学の音楽科に所属していたのですが、ちょうど進路を悩んでいたこともあって、卒業後に専門学校に通うことを決め、言語聴覚士の資格をとりました。
東北大学病院に入職されたのは?
初めは回復期のリハビリをしっかり経験したかったので、横浜市内の病院で脳血管疾患のリハビリを中心に診ていました。嚥下治療に力を入れている病院にも数か月間の研修に行かせもらいました。急性期のリハビリにも興味が出てきた頃に、縁あって地元の東北大学病院で働くことになりました。今は言語聴覚士として、嚥下機能障害だけではなく高次機能障害、言語発達障害、聴覚障害などのリハビリを担当しています。その中でも嚥下機能障害は、患者さんとご家族の“食べたい”“食べさせたい”という意欲が生きる希望になる反面、肺炎や窒息などの生死に関わるリスクが伴います。倫理的な観点も含め対応が大切であり難しい領域だと改めて感じています。
話は変わりますが、2019年にフィンランドオウル市への視察に参加されていましたよね
はい。実は父の主治医が脳神経外科の中川先生だったんです。当時からよく声をかけてくださっており、専門学校へ進学することなども相談していました。私が東北大学病院に入職すると、中川先生が主導されているASU(*2)で企業とのディスカッションの場に呼んでくださり医療の中でのビジネスモデルの話などを聞く機会に恵まれました。嚥下の領域でも様々な製品が開発されて実用化されています。私自身も現場でこんなモノがあったらいいなと思うことがあるのですが、嚥下のように個別対応が必要となる少数派ビジネスをどのように実現していくのだろうか、と考えることがありました。そんな時に院内でオウル大学病院の視察の募集があったんです。オウル市がAIを中心に街が発展していて、大学病院もその一部を担っていると聞いて、私も参加してみたい!と思い応募しました。ただ、メンバー表を見たら、そうそうたる面々で(笑)私なんかが参加していいのかと思いましたが、普段の仕事では関わることのない方々との交流は、今の取り組みにつながっています。 オウル大学病院ではAIを活用した医療テクノロジーについて、企業のプレゼンを聞く機会がありました。日本にすでにあるものでも、その国の文化や環境、ニーズに合わせた製品が開発が行われていて、AIといっても結局は人が組み立てていると知り、なるほど、と思いました。


視察団メンバー(当時)
[団長] 冨永悌二 病院長/脳神経外科・[副団長] 中川敦寛 病院長特別補佐/脳神経外科・亀井尚 副病院長/総合外科・植⽥琢也 病院長特別補佐/放射線診断科・佐々⽊百合花 副看護部長・工藤大介 救命センター・冨⽥尚希 加齢老年科・鈴⽊淳 耳鼻咽喉科・志賀卓弥 麻酔科・園部真也 脳神経外科・森山さや香 リハビリテーション部 言語聴覚士・前川正充 薬剤部・⼤塚佑基 臨床研究推進センター・⼩⽟亨 総務課総務係
今後の目標は?
視察をきっかけに他部署との新しい取り組みが始まっています。例えば総合外科の先生と術後の嚥下関連筋の廃用予防に関して電気治療を用いた予防的なリハビリを取り入れたり、歯学部の先生に、患者さんの発音の検査についての悩みを相談したら、それはAIで解決できるんじゃないか、そこからさらに発展できることもあるんじゃないかとアドバイスいただいて。専門の企業を紹介してくださり、AIを活用した研究が始まる予定です。これまで個人の感覚に頼っていた検査をAIで判断できれば、効率よく正確に検査することができるようになるのではないかと期待しています。 臨床でも研究でもシステム作りでも、何か新しいことを始めるには、医師はもちろん看護師さん、他多数のコメディカルスタッフ、事務の方との連携が必要です。日頃から相談しやすいつながりを持つことは診療にも良い影響があると感じています。私自身も自分の知識を惜しまず提供して、患者さんにも還元していきたいです。
プライベートではご趣味などありますか?
旅行やマラソンなどですね、ホノルルマラソンには2回参加しました。他には、大学の卒業生で結成した仙台市のオーケストラに所属してトランペットを演奏しています。今はコロナの影響で活動できていないので、早く落ち着いてほしいですね。

*1閉じ込め症候群:四肢麻痺および下位脳神経が麻痺しているが意識は覚醒している状態で、合図として用いる眼球運動以外、表情を示す、動く、話す、意思を伝達することができない。
*2 ASU(アカデミック・サイエンス・ユニット):企業がベッドサイドで現場観察をする環境を提供、現場のニーズから新たな製品開発などにつなげる取り組み